戒名の歴史 ― なぜ日本人は戒名を持つようになったのか
「戒名は死んでから付ける名前」と思われがちですが、歴史をたどると本来の役割はまったく異なります。戒名の歩みをたどることで、今なぜ戒名を授かるのか、その意味が見えてきます。
1)起源:戒名は “生きているうちに授かる仏弟子の名” だった
インドで仏教が成立した当初、仏の弟子になるには「受戒(戒律を授かる儀式)」を行いました。そのときに与えられたのが戒名です。つまり戒名とは、本来は生前につける宗教上の正式名でした。
この受戒と戒名授与の制度は中国で整えられ、東アジアの標準的な仏教の形として広まりました。
2)日本への伝来:仏教は伝来しても「戒」は無かった
仏教が日本へ伝わったのは6世紀ですが、当時の日本には正式な戒壇が無く、受戒そのものができない状態でした。転機は754年、鑑真和上を招聘し東大寺に戒壇を設けたことです。ここから日本でも正式に受戒と戒名授与が始まります。
そして、史上初めて戒名を授かった日本人は聖武天皇であったと伝えられています。当初、戒名は皇族・貴族・高僧など限られた存在のものでした。
3)江戸時代:庶民にも戒名が普及 ― 「死後名」へと転位
戒名が庶民にも広まる大きな契機は、江戸幕府が定めた「檀家制度」でした。すべての民衆がどこかの寺に属し、葬儀・法事を仏式で行うことが義務化されます。
この結果――
- 戒名は誰もが必ず授かるものに
- 生前授与ではなく葬儀時の授与が当たり前に
- 「戒名=死後の名前」という意識が社会に定着
本来は「仏弟子として生きる名」だった戒名が、制度上の要請により葬送儀礼のための死後名として機能するようになったのです。
4)現代:批判と再評価が同時に進む時代へ
近年は「無宗教葬」「戒名不要論」「戒名料批判」が増える一方で、同時に以下のような動きも広がっています。
- 葬儀を行わず戒名だけ授かるケース
- 遠方からの郵送・オンライン授与の増加
- 生前戒名(寿戒名)の復権
- 宗派・宗教不問の柔軟な対応
なぜ江戸以降、戒名は「高額」になっていったのか
近代に入ると「戒名は高い」というイメージが強まりました。これは単なる “暴利” ではなく、社会構造・制度・宗教観の変化が重なった結果として生まれた現象です。
1)檀家制度により「葬送=寺の仕事」が固定化された
江戸幕府は仏教寺院に「民衆の死亡確認・葬送・管理」を事実上任せました。寺が菩提寺として家を支える見返りに、戒名・法事・墓守りなどの宗教役務が継続的に依頼され、その戒名布施が成立していきます。
- 寺が「家の宗教的インフラ」になる
- 葬儀・戒名料は寺を支える経済基盤に
結果として、戒名は宗教行為と寺院維持を支える経済制度の一部となりました。
2)「位(ランク)」による差別化が始まった
戒名に「院号」「居士/大姉」などの尊称が加えられるほど、寺が丁重に回向し厚く祈りを尽くしたという社会的合意が生まれ、それが寄進・布施の額に反映されるようになりました。
- 位=その家の社会的体面と結びついた
- 「良い家は良い戒名を」という文化心理
こうして戒名に階層と寄進額の対応関係が成立し、金額が上昇していきます。
3)菩提寺との関係が「世襲」され続けた
檀家は一代限りではなく家として寺に属するため、「先祖代々の恩義・寺への信義」が長期に蓄積されました。そのため法事・寄進・戒名は先代の水準を維持または上回る形で授与されることが増え、金額は徐々に積み上がっていきます。
- 「父がこうだったから息子も同等に」
- 「ご先祖に恥じないように」という心理が作用
これが結果的に戒名=高額という現代の印象を形成しました。
単なる宗教儀礼の価格ではなく、共同体・家・宗教・経済が重なった結果として「高額化」したと位置づけられます。
生前戒名が今なぜ増えているのか
かつて戒名は「亡くなったあとに急いで授かるもの」が主流でした。ところが近年は、生きているうちに授かる「生前戒名(寿戒名)」を希望する人が急増しています。なぜ今、その流れが起きているのでしょうか。
1)「死の準備」はタブーではなく “当たり前の終活” になったから
エンディングノートや相続対策など、「死の準備」を前もって整えることは、いまや特別なことではなくライフプランの一部になりました。その延長として
- 戒名も人生計画のうちに前もって決めておく
- 葬儀の混乱をなくし家族への負担を減らす
という考え方が自然に受け入れられるようになっています。
2)「家の宗教」ではなく「自分の宗教」を選ぶ時代になったから
江戸〜昭和までは「家の菩提寺」が決めていました。しかし現代は──
- 実家の寺との縁が薄れた(転居・核家族化)
- 宗派にこだわらず自分で依頼先を選べる
- オンライン寺院・郵送授与など選択肢が拡大
「寺が決める戒名」から「本人が選ぶ戒名」へと構造が変わったことが背景にあります。
3)もしもの時に “バタバタして後悔した” という声が増えたから
突然の死別のあと、悲しむ間もなく決めることが山のようにあり、
- 「あの戒名で良かったのか」
- 「ゆっくり相談する時間が欲しかった」
という強い後悔の声が社会全体で共有されるようになりました。その反省から、「元気なうちに自分の意志で」という動きが支持を集めています。
4)「戒名の意義」を取り戻したい人が増えたから
戒名が「葬儀の形式」ではなく、
- 仏弟子としてどう生きたかを表す名前
- 残りの人生をどう歩むかの誓い
- 人生の区切りと感謝の表明
という本来の意味を理解した上で、信念として受けたい人が確実に増えています。
5)価格の透明化・自由化が進んだため
インターネットの普及により、戒名の費用相場が可視化され、菩提寺以外の選択肢も一般化しました。
- 「いくらかわからない」の不安が減少
- 無料・定額・相談可などの柔軟な授与も増加
これにより「生前のうちに余裕を持って依頼する」ことが現実的になりました。
- 生前戒名は、「死に備える暗い行為」ではなく「家族を困らせず、人生の意味を自分で決める」という能動的な終活として支持されています。
形式のためではなく、意義を取り戻すために──その選択は今、静かに増え続けています。
戒名に関する相談も多く寄せられています。戒名を改名と書かれる方もあり、死後の名前だとお考えの方も多くあるようです。そうすると、戒名の意味が忘れ去られ、戒名そのものがお金の問題になる。そうすると、戒名料が高い安いといった不満の声も増えてきているそうです。ここでは寄せられた相談を紹介すると共に、戒名とは何か?をお伝えしてきたいと思います
Q:浄土真宗で葬儀・初七日を済ませました。後で、日蓮宗だとわかりました。
Q:宗派がわかりません
Q:クリスタルの位牌でも魂入れは必要でしょうか?
Q:法名と戒名ってどういう違い、意味があるんですか?
Q:戒名は必要なものでしょうか。
戒名とは、何か?
仏教の教えを信じ、仏教徒として「仏弟子」となったときに、師匠から弟子に授かるのが戒名です。
現代では、亡くなってから授かる方がほとんどで、死後あの世での名前だと考えられています。
ご先祖のいる苦しみのない浄土に生まれ変わるのを願い、急ぎ戒名を授かり仏弟子として引導して、やすらかな成仏を祈ります。
戒名料なるお布施の問題がクローズアップされ、何のための戒名なのか?をお話ししてまいります。
戒名がないという方へ
突然の死別。何からすればいいのか?
(戒名のQ&Aは、下記に紹介しております。)
バタバタした葬儀を行い、悲しむ間もなく葬儀が進んでいく。宗派は?戒名は?戒名のランクは?とわからない事ばかり。
戒名は宗派によって呼び方が違います。
「戒名(かいみょう)」と呼ぶ宗派は、天台宗・真言宗・浄土宗・曹洞宗・臨済宗
「法名(ほうみょう)」と呼ぶ宗派は、浄土真宗
「法号(ほうごう)」と呼ぶ宗派は、日蓮宗
戒名・法名・法号とは何か?と問う前に、仏教とは何か?をお話ししてまいります。その上で、具体的な宗派の戒名について。
また、有名人の戒名一覧や自分で戒名を付けても良いのか?という内容について皆様から寄せられたお寺ネット仏事相談室より内容を踏まえまして、出来るだけわかりやすくお伝えしていきたいと思います。
- 葬儀を行ったが、まだ戒名がない方
- 自分の終活について戒名を考えている方
等の方にお役に立てれば幸いです
仏教とは何?

都会の方は、普段お寺との付き合いがない方が多くおられます。特には、高度成長期に田舎から都会に移り住み、家庭を持ち、初めて葬儀を経験されて大変な思いをされる。こんな相談も多く寄せられます。最近お参りに行ったお寺はどこですか?と質問すると菩提寺ではなく「浅草寺」や「東大寺」「薬師寺」といった観光目的のものがほとんどです。
そこで、本尊は?何をお参りしてきたの?と聞くと何も答えることはできませんね。
日本人のほとんどは「仏教徒」であるといわれています。
葬儀の9割が仏教で行われていると言われています。最近は、無宗教で行う方も増え、8割ぐらいに減少しているようですが、日本は仏教大国であるといって過言ではありません。それほど仏教を信仰している人が多いにも関わらず、あなたの宗教は?と質問すると「特にない。」「無宗教」という回答がかなりあるのではないでしょうか?
これは、不思議な現象ですね。
ほとんどの方が仏教徒であるはずなのに「無宗教」七五三や地鎮祭は、神社で。結婚式やクリスマスはキリスト教 葬儀になって急に仏教徒になるのが、日本独特の宗教感というか宗教システムであると思います。
仏教の始まりは、インド「お釈迦様」
皆さんこれはよくご存じですが、インドの教えが、日本に浸透し、日本に千年以上根付いているのです。お釈迦様の教えとは何か?様々な教えが(それをインドでは誇張して84000種類の教えがあるといわれます)ある中で、有名なのが般若心経に代表される「一切皆苦(人生は思い通りにならない)」と知ることから始まります。
一切皆苦(いっさいかいく)

なぜ苦しみが生まれるのでしょうか。仏教ではこの原因を、「諸行無常(すべてはうつり変わるもの )」で、「諸法無我(すべては繋がりの中で変化している)」という真理にあると考えます。これらを正しく理解したうえで、世の中を捉えることができれば、あらゆる現象に一喜一憂することなく心が安定した状態になる。
つまり、苦しみから解放される、とお釈迦さまは説かれています。これが、目指すべき「涅槃寂静(仏になるために仏教が目指す”さとり”)」です。
「一切皆苦」とは、人生は思い通りにならないという事を明らかにみる事からです。
まず、お釈迦さまは、私たちの世界は自分の思い通りにならないことばかりである、という真理を説いています。人は、生まれ・年を取り・病気になって・死んでいきます。これを、生老病死の四苦といいます。これに、愛別離苦(大好きな人とも別れなければならない苦しみ)・怨憎会(おんぞうえ)苦(会いたくない人に会わなくてはならない苦)・求不得(ぐふとく)苦・五陰盛(ごおんじょう)苦の四苦を加えて四苦八苦です。
「死ぬ苦しみ」そうです。だれも避けることなく、必ず死がやって切るのです。生あるものすべて亡くなります。その「死」の苦しみからの克服が宗教の第1義であります。また、「愛別離苦」 愛する人と別れなければならないという苦しみです。優しかったお母さんとも、たくましいお父さんともいつかは別れないといけません。愛する我が子ともです。小さな我が子が交通事故や病気などで親より先に亡くなる苦しみは想像に絶するものがございます。普段は、あまり考える事のない「死苦」しかし必ずやってくるのです。避けることが出来ません。平易にお伝えすると、仏教は、それをしっかりと見つめるのだと説きます。
思い通りにならないことを、思い通りにしようとするから苦しみのである。
それを克服した先に心の平安があるのだと説きます。その救いの為の方法には様々な方法があり、それを各宗各派の祖師・開祖・高僧が伝えてきたのですね。座禅を中心としたのが、禅宗であり、法華経を中心としたのが日蓮宗であり、浄土を中心としたのが浄土宗・浄土真宗です。
仏教は、釈迦に始まる
日本に伝わってきたのが、大乗仏教であり、まずは、奈良仏教(法隆寺や東大寺・薬師寺など)が広がります。

その後、平安仏教として比叡山 天台宗や高野山 真言宗が開宗されていきます。天台宗は、総合仏教と言われ、さまざまな仏教の教えが伝わってきました。お経とは、お釈迦様が書き写したものではなく、お釈迦様が説法をされた内容をお弟子様が聞いたことを文面化したものになります。ですからお経の始まりは「如是我聞」(われかくのごとき聞けり)として始まっているものが多くあります。
天台の教えを学んだ中で、難解な仏教を学ぶことではなく、「浄土経」と言われるお経から浄土に救いを求めたのが「浄土宗」であり、「浄土真宗」です。いや、座禅が一番だと、禅を中心に置いたのが禅宗と言われる「曹洞宗」「臨済宗」です。いやいや法華経が一番素晴らしいと説いたのが「日蓮宗」であります。
天台のお経は、朝題目に夕念仏といわれるのは、両方のいいとこどりを取ったわけではなく、現代の教えを学んである姿勢であり、浄土宗や日蓮宗は、専門特化したといっても良いでしょう。
日本人で戒名を初めて授かったのは、聖武天皇
日本に仏教が伝わったのが538年と言われています。しかし、それから200年ほど過ぎて、仏教は伝わっても「戒律」が授かっていないとなります。仏教徒になるには、戒律を授かることが仏教徒になる資格でもあります。
その戒律とは、日本では、五戒
1.不殺生戒(殺すな)
2.不偸盗戒(盗むな)
3.不邪淫戒(みだらな異性関係を持つな)
4.不妄語戒(嘘をつくな)
5.不飲酒戒(酒を飲むな)
この戒律を御仏の前で誓った時、仏教徒となり、仏弟子となるのです。

改名ではなく、戒名です。
しかし、その後 浄土真宗 親鸞さんや、日蓮宗 日蓮さんの登場で変わってきます。
戒名と法名の違いにつて戒名や法名は、どちらも仏弟子になる際に授けられる二文字の名前(仏名)です。戒名と法名の違いは、根本的な教義の違いになります。
仏教には、「戒律」と呼ぶ修行者の生活規律があり、すべての修行者は常に戒律を守らなければなりません。
先に挙げた、五戒を守り(在家の場合五戒 僧侶の場合は十戒ともいわれます)西遊記で有名な「三蔵法師」は、一人ではありません
玄奘三蔵や羅什三蔵など、仏教を伝えた仏教者の事をさします。三蔵とは、「戒」「律」「論」を伝えた方という意味です。
自発的に規律を守りたい心の表れを意味する「戒」と、信条や規則を指す「律」お釈迦様の教えに基づいて論じられた「論」
戒律は、規則だはなく、自らを律する誓いであります。人は、戒律を守ることは原則不可能なことです。しかし、一つでも抑えた生活を送るための誓いです。例えば、「不殺生戒」殺すのは、人間だけでなく、動物であったり植物も意味します。お米であり花であり、すべてに命が宿っていますこの命を奪わなければ私たちは生きていくことが出来ないのです。
ただ、その命を少しにする。すこしでも命を大切にしていく。この心掛けがあるのとないのでは大きな違いがある事でしょう。
このように、一つ一つ 一人一人の命を大切にして、仏道修行に励むことです
法名は、全部お任せ

法名は、私たちは凡夫であって、修行をして悟ることなどできない。すべては、阿弥陀如来のおはからいである。修行ではなく生活のなかで阿弥陀仏の慈悲にすがって生きるのです。浄土真宗の元来の教えは、厳しい戒律を守って修行できない人が阿弥陀如来の働きによって救われて仏となるものです。
浄土真宗には、戒律がないので受戒が存在しません。受戒の代わりとして、仏法をよりどころとして生活する証として法名を授けられます。門徒として生きる誓いを立てるものです。
阿弥陀仏の教えを守りながら生きていくことを誓うものであるためです。
日蓮宗では、戒名とは言わず法号
日蓮宗では、「法華経を護持することは持戒に勝る」として戒名とは言わず法号といいます。文字は、二文字であり、戒名と同じです。戒律を守って生きていくのか?法華経を護持して生きていくの?阿弥陀様にお任せして生きていくのか?これによって、根本的に違ってくるのです。
貴方はどのような生き方が良いでしょうか?そうです。戒名は、元来生きている人が授かり、仏教徒として歩むためのものです。決して死んでからのものではないのです。この機会に、各宗派の教えを学び、ご自分がぴったりくる教えに触れて、楽しく・優しい人生を歩まれることをお祈りしております。
戒名Q&A お寺ネット仏事相談から
お寺ネットでは、仏事相談室を開設し、様々な仏事の無料相談をお受けしております。また、NPO法人かけこみ相談センターでは、実際にメールや電話zoomなど匿名ではなく直接の仏事相談も承っておりますそのような仏事相談(令和3年9月22日現在 5701番)から、具体的な内容を紹介してまいります。お急ぎの方は、メールでご相談ください。急ぎお返事申し上げます
宗派による具体的な戒名の違いについて
天台宗の戒名
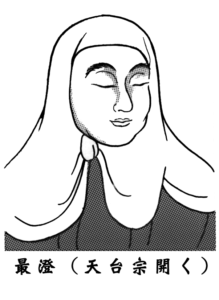
<教義>
釈迦の多くの経文の中で最高の経とされる「法華経」を中心におき「人は誰でも仏になれる種子があり、縁にふれて努力すれば成仏できる」と教えている。
天台宗の教義は、総合仏教でありましたので、浄土宗の法然 臨済宗の栄西 曹洞宗の道元 浄土真宗の親鸞 日蓮宗の日蓮といった各宗祖も、この比叡山で学ばれ、その教えの専門的な事を説かれ、広められていきます。
<ご本尊>阿弥陀如来(釈迦如来、薬師如来をまつる事もある)
真言宗の戒名
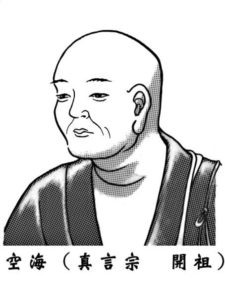
<教義>真言とは仏の真の言葉、それを身・口・意、つまり心と体で体得しようと努めていけば即身成仏できると説く教え。
<ご本尊>大日如来<本山>高野山金剛峯寺<宗祖>弘法大師(空海)西暦816年
<諸派>高野山(金剛峯寺)、智山派(智積院)、豊山派(長谷寺)
<経典>大日経、金剛頂経、理趣経、般若心経
曹洞宗の戒名
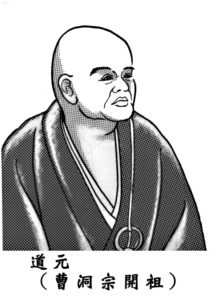
<教義>
私たちが人間として生を得るということは、仏さまと同じ心、「仏心(ぶっしん)」を与えられてこの世に生まれたと、道元禅師はおっしゃっておられます。「仏心」には、自分のいのちを大切にするだけでなく他の人びとや物のいのちも大切にする、他人への思いやりが息づいています。しかし、私たちはその尊さに気づかずに我がまま勝手の生活をして苦しみや悩みのもとをつくってしまいがちです。
お釈迦さま、道元禅師、瑩山禅師の「み教え」を信じ、その教えに導かれて、毎日の生活の中の行い一つひとつを大切にすることを心がけたならば、身と心が調えられ私たちのなかにある「仏の姿」が明らかとなります。
日々の生活を意識して行じ、互いに生きる喜びを見いだしていくことが、曹洞宗の目指す生き方といえましょう。(曹洞宗公式サイトより)
<ご本尊>釈迦牟尼仏
<本山>永平寺・総持寺
<宗祖>道元禅師 西暦1227
<経典>般若心経・観音経・修証義・法華経
臨済宗の戒名
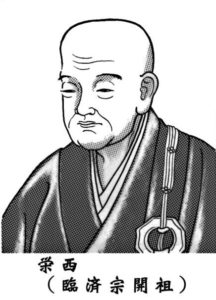
<教義>日常の一挙一動が道の働きであり、「平常心これ道」と説く。道は理想を求めず日常の中にあるとする。
<禅とは>
ひとつの相にこだわらない無相。一処にとどまらない無住。ひとつの思いにかたよらない無念の心境を禅定と呼び、ほとけの心のことです。私たちの心は、もとより清浄な「ほとけ」であるにも関わらず、他の存在と自分とを違えて、対象化しながら距離と境界を築き、自らの都合や立場を守ろうとする我欲によって、曇りを生じさせてしまいます。
禅とは、雀の啼き声を耳にしても障りなく、花の香りの中にあっても妨げにならず一如となれる、そういう自由自在な心のことです。(妙心寺のホームページより)
<ご本尊>釈迦牟無尼仏
<本山>建仁寺(それぞれの派により異なる本山を持つ)
<宗祖>栄西禅師 西暦1202
<諸派>(妙心寺・南禅寺・建仁寺・建長寺・円覚寺)
浄土宗の戒名
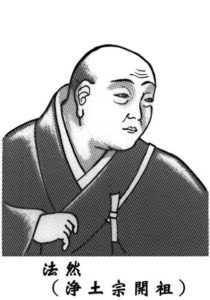
<教義>称名念仏を全ての修行に優先する。
<ご本尊>阿弥陀如来<本山>知恩院<宗祖>和順大姉(法然)西暦1175年
<経典>浄土三部経:無量寿経、観無量寿経、阿弥陀経
浄土真宗の法名
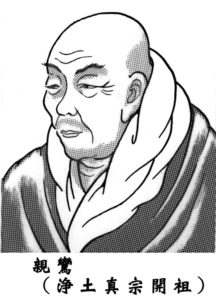
<教義>弥陀の積善が廻向されて、それに乗って衆生が浄土に往生できるとする、絶対他力の教え。念仏をもっぱらにして阿弥陀如来の本願を信じる事をつとめとする。
<ご本尊>阿弥陀如来<本山>東本願寺<宗祖>見真大師(親鸞1224)西暦1602年
<経典>浄土三部経:無量寿経、観無量寿経、阿弥陀経
日蓮宗の法号
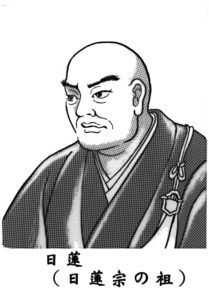
<教義>久遠実成の釈迦牟尼仏にむかい「南無妙法蓮華経」の題目を唱える事で即身成仏し、理想の社会であるフ仏国土が実現すると教える。
<ご本尊>曼荼羅(南無妙法蓮華経の7字)<本山>身延山久遠寺<宗祖>日蓮聖人 西暦1253
<経典>法華経
日本の7大宗派に分けて、戒名の説明をしております。
生前戒名を授かる
戒名は、元来生前に授かるものでございます
各宗派においても、授戒会という生前戒名を授ける儀式を行っておられますので、出来れば生前のうちに戒名をお授かりになることをお勧めします
お坊さんへのアンケートメッセージ
戒名とは何か?基本のQ&A
Q1. 戒名とは何ですか?
A. 戒名とは、亡くなった方に授けられる「仏弟子としての名前」です。死後、仏の弟子となり成仏することを願って授与されます。
Q2. 法名や法号との違いは?
A. 宗派によって呼び方が違います。浄土真宗では「法名」、日蓮宗では「法号」禅宗(曹洞宗・臨済宗・黄檗宗)や真言宗、天台宗・浄土宗では「戒名」と呼ばれますが、意味は同じです。
Q3. 戒名がないと成仏できない?
A. 成仏とは、仏教の意味であり戒名がないと成仏しません。キリスト教や神道などでももちろん成仏はしません。そのように仏教として行うのであれば、戒名は仏弟子としての証であり、供養や安心のために大切な役割を果たします。
Q4. 戒名の歴史は?
A. 戒名の習慣は奈良・平安時代から始まり、武士や庶民に広まったのは江戸時代以降といわれます。
Q5. 戒名は日本だけ?
A. 中国や韓国にも同様の習慣はありますが、日本ほど広く普及しているのは特徴的です。
戒名を授かる方法に関するQ&A
Q6. 誰から戒名を授かるの?
A. 一般的には菩提寺の住職や依頼した僧侶から授かります。戒名は、あくまで師僧から授かるものです。
Q7. 僧侶なら誰でも付けられる?
A. はい。得度を受けた僧侶であれば戒名を授与できます。
Q8. 葬儀社に頼むのは普通?
A. 最近は葬儀社経由で依頼する方も多いですが、直接お寺にお願いする方が安心です。
Q9. 葬儀時に必ず授かるの?
A. 本来は、生前に受けることですが、その仏縁がなかった場合急ぎ、葬儀で授与されます。これが一般的になりました。
Q10. 生前戒名とは?
A. 「寿戒名」とも呼ばれ、生きているうちに授かる戒名です。安心して余生を過ごすために希望する方が増えています。
Q11. 遠方から依頼できる?
A. はい。郵送やオンライン(Zoom・メール)での授与も増えています。
戒名の費用に関するQ&A
Q12. 戒名料はいくら?
A. お寺や地域で差がありますが、数万円〜数十万円。
Q13. 戒名料の相場は?
A. 一般的には30万〜100万円と言われますが、お布施ですので明確な基準はありません。
Q14. 無料で授かれることもある?
A. 菩提寺との縁が深い場合や特別な事情がある場合、無償で授けられることもあります。経済的にお困りの方にはインターネットから無料でお授けしているお寺もあります。(本寿院の無料戒名)
Q15. 高い戒名と安い戒名の違いは?
A. 一般的には「院号」「居士」「大姉」などの尊称が加わると高額になります。院号は、天皇陛下が寺院を建立されたことに始まります。それほど仏教に厚く信仰し、仏教に貢献したという意味です。
Q16. お金がないと戒名はもらえない?
A. そんなことはありません。費用を抑えて授与する寺院もあります。
Q17. 戒名料は分割できる?
A. お寺によっては分割や相談に応じてもらえる場合もあります。
戒名の内容・ランクに関するQ&A
Q18. 戒名はどう決まる?
A. 故人の人柄や生前の功績、家族の希望などを考慮して決まります。
Q19. 院号とは?
A. 功績のあった人や特別な布施をした人に授けられる尊称です。
Q20. 居士・大姉とは?
A. 居士は徳のある男性、大姉は徳のある女性に授けられる尊称です。
Q21. 信士・信女とは?
A. 最も一般的な戒名の呼称で、広く用いられます。仏教信者という意味です。
Q22. 戒名は長いほど立派?
A. 長さは立派さとは関係ありません。意味が大切です。
Q23. 戒名に好きな文字を入れられる?
A. お授けするご僧侶に相談されてください。趣味や人柄を表す文字を伝えておくことは可能です。
Q24. 家族で同じ院号はできる?
A. いいえ。戒名はその方の生き方をあらわすもので、苗字ではありません。ですから同じ院号というケースはほとんどございません。
宗派による違いのQ&A
Q25. 浄土真宗の法名と戒名の違いは?
A. 浄土真宗では「法名」と呼び、居士・大姉といった尊称を付けないのが特徴です。ただ、地方のお寺によって特殊なケースもあります
Q26. 禅宗の戒名は?
A. 禅宗では「道号」を重んじ、修行や徳を反映させます。
Q27. 真言宗の戒名は?
A. 大日如来の教えを反映させた漢字を用いることが多いです。
Q28. 日蓮宗の戒名は?
A. 日蓮さんの「日」の字が入るのが特徴です。
Q29. 宗派を変えると戒名も変わる?
A. 必ずしも変える必要はありませんが、宗派によって呼称が異なる場合があります。
特殊なケースに関するQ&A
Q30. 子どもにも戒名は付けられる?
A. はい。幼い子には「童子」「童女」などを使います。
Q31. 水子に戒名は?
A. 水子供養で戒名(法名)を授けることもあります。
Q32. ペットに戒名は?
A. ペット供養で戒名を授けるケースもあります。
Q33. 外国人でも戒名をもらえる?
A. はい。国籍に関係なく授与可能です。
Q34. 無宗教でも戒名は必要?
A. 必須ではありませんが、供養や安心のために授ける方もいます。
戒名の変更・付け直しに関するQ&A
Q35. 戒名を付け直すことは可能?
A. はい。経済的事情などで簡易な戒名を選んだ場合に後から変更できます。
Q36. 戒名をもらい直すことはある?
A. 他宗派から本宗に改める場合などに行われます。
Q37. 戒名を直すと迷うのでは?
A. いいえ。供養のための変更であり、故人を敬う行為です。
戒名と供養の関係Q&A
Q38. 戒名がないと葬儀はできない?
A. 基本的に、仏弟子として授戒する儀式が葬儀であり戒名がないと出来なものです。しかしながら、菩提寺が遠方にあり、仮通夜や密葬と言わる身内だけの場合は俗名で行い、菩提寺で本葬をされます。現在では、その事が忘れられていて、費用がかかるのであれば簡素に俗名でと判断される方が多くなりました
Q39. 戒名がないとお墓に入れない?
A. 墓地によっては戒名を必要とする場合があります。無宗教のお墓であれば必要ありません。
Q40. 戒名は位牌に必ず書く?
A. 多くの場合、位牌には戒名が刻まれます。俗名の位牌は意味がありません。ただし、浄土真宗は、位牌を作らず過去帳や法名軸に書かれます
実務的な質問Q&A
Q41. 戒名をお願いする手順は?
A. 僧侶に相談 → 必要事項を伝える → 法要で授与、が一般的な流れです。
Q42. 依頼から授与までの期間は?
A. 早ければ即日〜数日。葬儀の場合は急ぎで対応します。
Q43. 必要な情報は?
A. 故人の俗名、生年月日、亡くなった日、仕事、趣味や人柄などです。
Q44. お布施以外に必要?
A. 基本はお布施のみです。特別な法要があれば追加費用が発生する場合もあります。
戒名の意味・功徳に関するQ&A
Q45. 戒名の本当の意味は?
A. 仏弟子となり、仏教徒として新たな名前で生まれ変わることを意味します。
Q46. 戒名で来世は変わる?
A. 成仏は授戒し、戒名を授かる事で、信仰心や供養によって導かれるものです。
Q47. 戒名をいただく功徳は?
A. 故人が仏弟子として加護を受け、遺族も安心できる心の支えになります。
ネットで戒名授与に関するQ&A
Q48. ネットで戒名をつけるお寺に依頼する方法は?
A. 電話・メール・公式サイトのフォームから依頼できます。
Q49. 宗派は関係ある?
A. いいえ。宗派問わず、どなたでも授与できます。
Q50. 戒名授与後は法要もできる?
A. ご希望に応じて葬儀・法事・永代供養まで対応しています。
特殊なケースに関するQ&A
Q51. 子どもにも戒名は付けられますか?
A. はい。幼児や子どもにも戒名は授けられます。幼くして亡くなった場合は「童子」「童女」などの字を用いることがあります。
Q52. 水子にも戒名を授けられますか?
A. 水子供養に際して戒名や法名を授けることがあります。両親の祈りを込めてお授けすることで、心の癒しにもつながります。
Q53. ペットにも戒名は付けられますか?
A. はい。現代ではペットも家族の一員として供養され、戒名や法名を授けるお寺も増えています。
Q54. 生前に戒名を受ける人は多いですか?
A. 増えています。安心して余生を送るためや、家族に迷惑をかけないために生前戒名を希望する方が年々増加しています。
Q55. 無宗教でも戒名を授かれますか?
A. 可能です。宗派にとらわれず、供養のために戒名を希望される方も多くいます。
Q56. 外国人でも戒名をもらえますか?
A. はい。国籍や信仰に関係なく、ご本人やご家族が希望されれば戒名を授けることができます。
Q57. キリスト教徒が戒名をもらうことはありますか?
A. 稀ですがあります。仏教の供養を望む場合や家族の希望で戒名を授かるケースも存在します。
Q58. 葬儀をせずに戒名だけ授かることはできますか?
A. はい。葬儀を行わず、戒名のみを授かり、後日納骨や法要を行う方もいます。
Q59. 海外在住でも戒名をお願いできますか?
A. 可能です。インターネットや郵送を通じて戒名を授かることができます。
Q60. 改葬の際に新たに戒名を授けることはありますか?
A. 必要に応じて行うことがあります。受け入れ先のお寺の指示に従うと安心です。
戒名の変更・付け直しに関するQ&A
Q61. 戒名を付け直すことは可能ですか?
A. はい。経済的事情や希望に応じて後から付け直す方もいます。
Q62. すでにある戒名をもらい直すことはできますか?
A. 可能です。事情によりよりふさわしい戒名を新たに授かることがあります。
Q63. 高位の戒名に変更できますか?
A. 希望に応じて院号などを加えることが可能です。追贈として授けられます
Q64. 間違って刻んだ戒名は修正できますか?
A. はい。位牌や墓石に刻んだ戒名の修正も可能です。ただし住職と仏壇店・石材店に相談しましょう。
Q65. 複数の戒名を持つことはありますか?
A. 稀ですが、宗派を超えて授与された場合などに複数の戒名を持つケースがあります。
Q66. 他寺院で授かった戒名を直せますか?
A. はい。インターネットで授かる本寿院では、宗派に関わらずご相談いただけます。
Q67. 戒名を変えると故人が迷うのでは?
A. そのような心配は不要です。よりよい供養を願う心が大切です。
Q68. 亡くなった後に戒名を変更するのは失礼では?
A. 故人を敬い、供養の思いを込めるための変更であれば問題ありません。
Q69. 戒名に俗名を取り入れられますか?
A. はい。俗名の一部を取り入れることで、故人を偲びやすくなります。
Q70. 芸名やペンネームを戒名に使えますか?
A. 特別な希望があれば考慮していただける場合があります。
戒名と供養・法要に関するQ&A
Q71. 戒名がないと葬儀はできませんか?
A. 俗名のまま葬儀を行うことも可能です。ただし戒名があるとより正式な供養となります。
Q72. 戒名がないと法事はできませんか?
A. できます。ただし位牌や過去帳に俗名を記す形になります。
Q73. 戒名がないとお墓に入れませんか?
A. 墓地や納骨堂によっては必要とされる場合があります。
Q74. 納骨堂に戒名は必要ですか?
A. 必須ではありませんが、記録や銘板に戒名が刻まれることが一般的です。
Q75. 戒名があると供養は変わりますか?
A. 供養の形式が整い、故人を仏弟子として弔うことができます。
Q76. 戒名があると極楽に行けるのですか?
A. 戒名そのものが保証するわけではありません。信仰と供養の心が大切です。
Q82. 戒名はどのくらいで授与されますか?
A. 急ぎの場合は即日、通常は数日以内です。
Q77. 戒名がないと魂は迷うのですか?
A. 迷うことはありません。ただし戒名は仏の弟子となった証として遺族に安心を与えます。
Q78. 法要のとき戒名は必ず読み上げられますか?
A. はい。回向や読経の際に戒名を唱えるのが一般的です。
Q79. お経の中で戒名はどう扱われますか?
A. 故人の戒名を唱え、仏の加護を祈る形で読み上げられます。
Q80. 戒名は位牌に必ず刻まれますか?
A. ほとんどの場合刻まれますが、俗名を記すことも可能です。
実務的な質問Q&A
Q81. 戒名を依頼する流れは?
A. 僧侶に相談 → 情報を伝える → お布施を納める → 法要で授与、という流れです。
Q94. 戒名は供養を受けるために必要?
A. 必須ではありませんが、供養の際に故人を特定しやすくなるため重要です。
Q83. 戒名依頼に必要な書類はありますか?
A. 基本的に不要ですが、死亡診断書や戸籍を確認する場合もあります。
Q84. 戒名をお願いするときの注意点は?
A. 宗派や寺院の考え方を確認し、費用や内容を事前に相談することが大切です。
Q85. 遺族が戒名を決めるのですか?
A. 基本的には住職が決めますが、遺族の希望を反映することもできます。
Q86. 戒名は住職が一方的に決めるの?
A. いいえ。多くは家族の意向を尊重し、相談の上で決められます。
Q87. 戒名をお願いすると法要も付いてきますか?
A. お布施に含まれる場合と、別途費用が必要な場合があります。
Q88. 戒名は戒律を受けた証ですか?
A. 戒名は仏弟子となった象徴ですが、浄土真宗のように戒律のない宗派もあります。
Q89. 戒名は菩提寺でしか授かれませんか?
A. 必ずしもそうではありません。全国どこからでも依頼可能です。
Q90. インターネットでの戒名授与は本当に大丈夫?
A. 信頼できるお寺であれば問題ありません。本寿院でも公式にオンライン対応しています。
戒名の意味・功徳に関するQ&A
Q91. 戒名の本当の意味は何ですか?
A. 戒名は「仏弟子として新たに生まれ変わる証」です。
Q92. 戒名で来世は変わりますか?
A. 来世は戒名の有無ではなく、信仰や供養の心によって導かれます。
Q93. 戒名を授かる功徳は?
A. 故人が仏弟子として導かれ、遺族が安心を得られるという大きな功徳があります。
Q95. 戒名が立派だと子孫に良い影響がありますか?
A. 直接的な影響はありませんが、供養に誠意を込める姿勢が子孫に受け継がれます。
Q96. 戒名の位が高いと極楽に行きやすいのですか?
A. 位の高さで成仏が決まるわけではありません。
Q97. 戒名をいただくことで遺族は安心できますか?
A. はい。故人が仏の弟子として守られているという安心感を得られます。
Q98. 戒名はお墓や仏壇と関係しますか?
A. 多くの場合、お墓や仏壇、位牌に戒名が刻まれ、後世の供養に欠かせません。
Q99. 戒名の有無で遺族の心は変わりますか?
A. 戒名をいただくことで「供養を尽くした」という安心感を持てます。
Q100. 戒名をお願いする方法は?
A. 電話・メール・インターネットサイトから依頼できるお寺もあります。3万円で戒名を付けてくれるお寺もある。

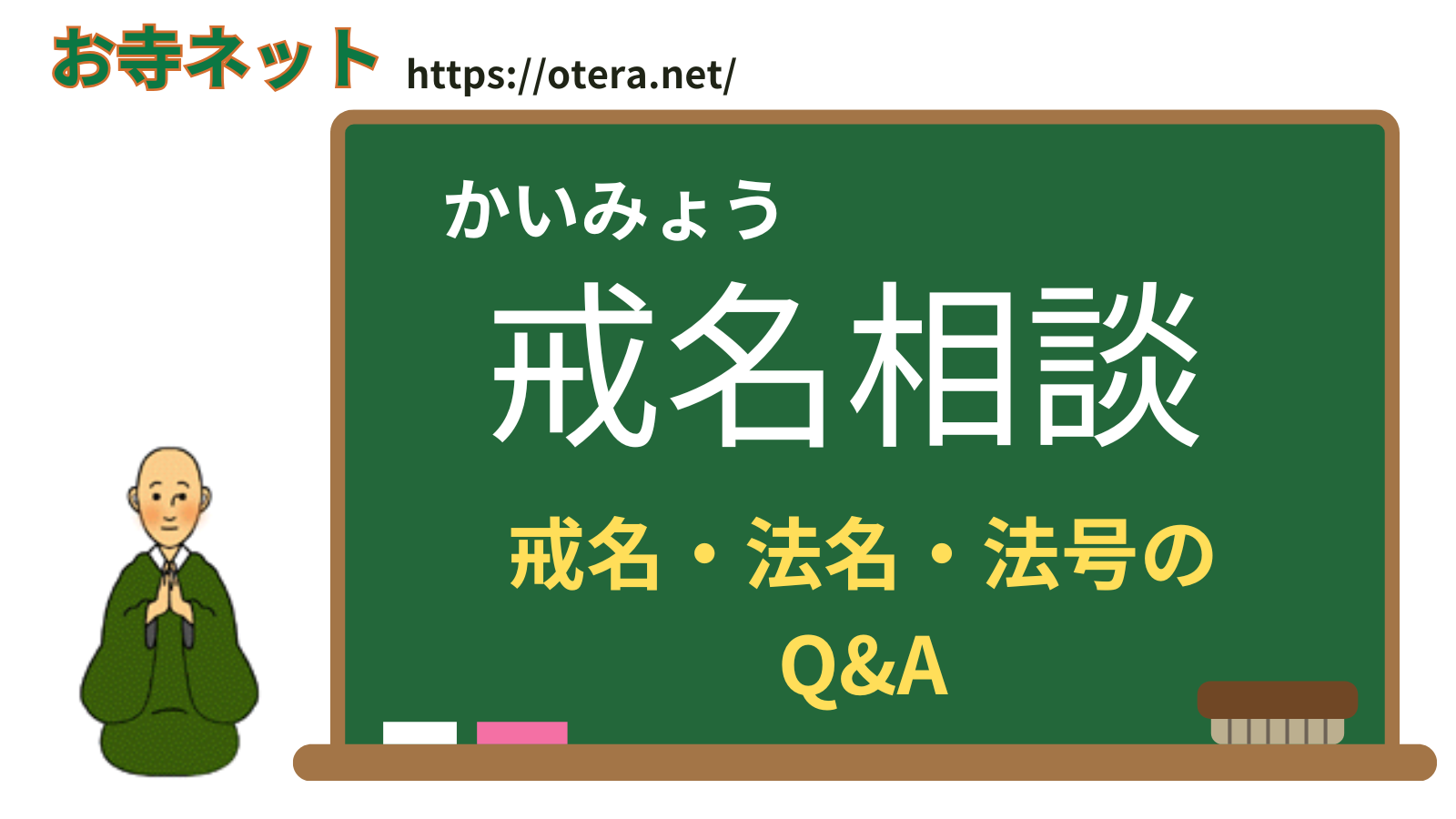
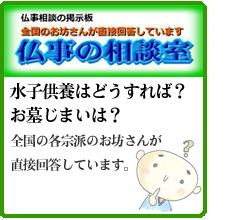

皆さんの貴重なご意見をご投稿ください。