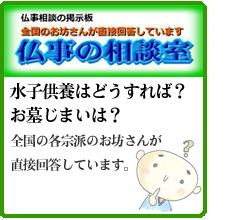葬儀の流れ・手順
葬儀に関して、仏事の相談室にもたくさんの相談が寄せられています。一番悩むのが「お布施」の事。あくまでお気持ちではありますが、高いのか?安いのか?わからなくて困るという方も。また、お布施に関して僧侶への怒りに満ちた不満をぶつける方もございます。葬儀は何をしているのか?戒名は必要なのか?様々な疑問を抜粋して紹介すると共に、下記には実際に葬儀の時に必要な情報を紹介させていただいております。
Q:戒名につき相談したところ、会計の担当者の方に200万
Q:葬儀のお布施代戒名代のみで100と言われ同じ檀家に聞いて倍の200収めました
Q:元職場の主任さんが8月18日金曜日の早朝の通勤時に交通事故により、他界された
Q:納骨を一周忌まで待って欲しいとお寺さんにお願いすると「魂が一年間迷うことになるが、それでもよいか?」
Q:お布施をお渡しした際、「中身を見ますが、金額は大丈夫ですか」と。
葬儀とは、悲しいかなお亡くなりになった大切なご家族を弔い、幸せな次の世界に誘う重要な儀式です。
仏教では、極楽浄土 キリスト教では、天国と言われます。
宗教によって、様々な死生観がございますが、仏教においては、「浄土」が基本となります
浄土とは、御仏のおられる世界をさします。
宗派によって、その浄土の場所がかわってきますので、ご注意ください
天台宗・浄土宗・浄土真宗は、「極楽浄土」
真言宗は、「密厳浄土」
日蓮宗は、「霊山浄土」
曹洞宗・臨済宗は、浄土をたてません。
この様に、宗派によって考え方がわかってきます。それは、長い時間の中で、それぞれの宗派で培われてきた世界観です。
ただし、仏教の根本にあるのは、死んでからの物ではなく、生きているうちでの悟りを目指すものであり、簡単な旅行切符のようなものではありません。この機会に宗派の葬儀・考え方について学ばれることをおすすめします。
葬儀の流れ

ここでは一般的な葬儀の流れ・手順をご紹介し、お葬式準備にお役立ていただければ幸いです。
※下記の流れは一例になり、葬儀社や地域によって内容は異なります
1. ご臨終
2. お迎え〜ご遺体搬送
3. ご遺体安置
4. 葬儀のお打ち合わせ・準備
5. ご納棺
6. お通夜
7. 告別式
8. お別れの儀式・ご出棺
9. 火葬
10. 初七日法要と精進落とし
11.後飾りと諸手続き
12. ご納骨・四十九日
お葬式後
具体的な方法についてお話してきます。
1. ご臨終

危篤状態になると、病院から連絡が入ります
そして出来る限りの延命措置をして下さいます。
少しでも、遺族の方が死に際に立ち会えるようにしてくださいますが、当然状況によります。
(私の場合は、連絡があり駆けつけましたが一生懸命心臓マッサージなど延命措置をしていてくださいました。その姿を見て、「ありがとうございました」としかいうことが出来ませんでした。そうして、医師が時間を見て「〇〇時〇〇分 ご臨終です」と告げてくださいました)
2. お迎え〜ご遺体搬送
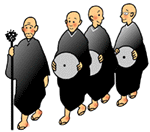
現在では、ほとんどの場合、病院でお亡くなりになります。
病院では、すぐにお迎えに来ていただく必要があります。
なぜなら、それまでは、一般病棟もしくは、集中治療室に治療されていましたが、亡くなってしまうと、その後は病院の仕事ではありません。もっとも、亡くなったからと言って、同じ病室に戻すことも不可能です
誰だって、同室に遺体があれば、ゆっくり寝ることは出来ないですね。
それだけでなく、感染症の危険もあります。ご遺体は、命がなくなると、すごい早いスピードで腐敗していきます
その為に、ドライアイスなどお身体を冷やす必要があります。しかし、ドライアイスも二酸化炭素を排出するため危険であるとと最近言われるようになりました
また、冷凍保存となりますが、霊安室に保管用冷凍室を持っている病院は少なく、亡くなって湯灌後(たいていの病院では最後のおみぬぐいをしてくださいます)数時間後にはご自宅に搬送していただきます
安全に遺体を保存するには「エンバーミング」しかありません
3. ご遺体安置
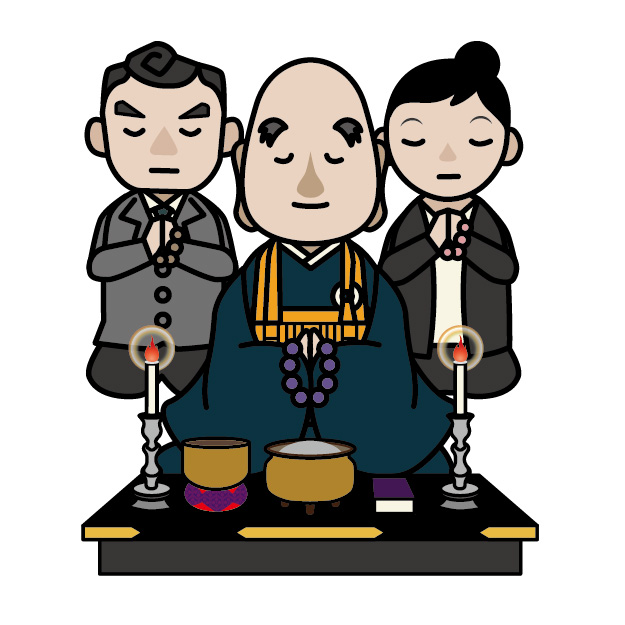
ご遺体の安置場所をどうするか?これが簡単ではありません。
故人は、当然長い間自宅から離れて入院生活を送っている場合が多いので自宅に戻りたいと考えます。
しかし、動かない遺体を自宅に迎えるのは、とても大変な作業となります。
ご自宅が、一軒家か、マンションなど集合住宅なのか?
一軒家の場合について
玄関もしくは窓から遺体を搬送します。玄関が広い場合は問題ありませんが、遺体は横たわっていますので横向きで入る事を考える必要があります。
そして、ご自宅のどこに安置するか?
今後、祭壇をつくり、弔問客をを迎えるわけですので、出来るだけ玄関に近くて、導線(入り口から出口まで)が流れやすいことが大切です。
また、その場で通夜・葬儀と法要を行うわけですので、それなりの広さが必要です。
遺体を安置してから、葬儀まで通常3~4日かかります。その間、ドライアイスや保冷剤 祭壇などしつらえますので、普段の生活に支障がないことをお考え下さい。(毎回トイレに行くにはその前を通らないといけない。食事場所・ダイニングである。受験生の勉強部屋など)
ご自宅で安置する事の注意点
1点目 葬儀の形式をどうするか?
あらかじめ考えておかれることをおすすめします。
最近は、家族葬といって、身内だけの少人数で行う方が多くなってきています。また、コロナの問題で、本当に数名で送るというケースが増えてきております。
自宅で行うという事は、近所の方に知られることになります。
案内をしなくとも、近所の手前、ほっておくことは出来ず、何かしらの弔問にお越しになります。
昔から、「村八分」という諺があるように、普段は、一切付き合いをしないけれど、2分(葬式と火事)の時だけは、地域で互助するといわれます。
誰にも言わず行う事は、まず難しく、地域の町内会長などがお越しくださいます。
2点目は、駐車場の確保
弔問者がある場合、車を利用される方が多くあります。
しかし、自宅の場合事前に駐車場を確保している方は少ないのがほとんどです。
ですから、路上駐車などすると、反対に近所迷惑となりますので、その間だけ、近くの駐車場をかりる手配が必要です。
3点目は、食事の問題
昔の家は、広く設計されていましたので問題ありませんでしたが、通夜終了後、通常は食事をふるまいます。
ほとんどの方は、そこで、食事やお酒を飲んで故人をしのびます。

長居される方は少ないですが、その為の準備をしておかなくてはなりません。昔は、近所の方が総出で食事を作りお手伝いしてくださいました。しかし、今では、そのような近所付き合いはかえって大変だという考えから、仕出し屋さんの料理をふるまうケースがほとんどです。
しかし、それも座って食事をするスペースが必要となります。
お寺で行う場合
少し前までは、お寺で行う場合が多くありました。しかし、お寺と言って自由に出来ることは少なく、菩提寺さんの本堂をかりるわけですので、それ相応のお礼が必要となります。
最近は、上記の理由から、ほとんどが葬儀会館を利用されるます。
ただ、昔の葬儀を取り戻そうと、葬儀社主導の葬儀の流れから、寺院主導の葬儀の流れにかえていこうという、仏教会の試みもあります。現実問題として増えているとはいいがたいことでありますが、慣れ親しんだ菩提寺で行えることはとても良いことです。
4. 葬儀のお打ち合わせ・準備
ご自宅まで搬送して下さった業者さんが、実は葬儀社の方であったというケースは多くあります。
もっとも、搬送のみで終わる業者さんもあるでしょうが、まずは、どちらに遺体を安置するのか?が問題となります
よく言われる、公営の斎条での葬儀は、安く済むとお考えの方は多くあります。
実際、葬儀の会館使用料などは、ほかとくらべて格安です。
しかし、斎場を利用する際の注意点もあります。
人気がある事から、利用まで数日間待つ必要があります。
病菌からすぐに公営の斎場に遺体を運ぶことは難しく、いったんどちらかに安置する必要があります。
ちゃんとした安置場所を用意している葬儀社であれば、問題ありませんが、無い場合は提携の安置所など冷凍保存する必要があります。この遺体安置料が、一日数万円かかる場合もあり、それが1週間先の葬儀となった場合、ドライアイス代や保管料等気が付くと結構な値段になる場合もあります。この点が見落としがちですのでご注意ください。
葬儀の打ち合わせは、やらなければならないことが、一瞬のうちに決まっていきます。
喪主は悲しんでいる暇はないぐらいです。
まずは、日程をいつにするか?
友引は斎場が休みだという地域も少なくありません。友引は、語呂の問題で、一緒にあの世にひかれてしまうという事から葬儀をすると、会葬者が縁起が悪い(表現が違いますが・・・)と参加されません。ですから友引を避けて行い事が大切です。(本来の語源は、その時は相撲など勝負事は勝敗がつかないのでやめましょう。という意味ですので元来葬儀とは全く関係のないものです。事実、京都ではそれは迷信であると友引関係なく葬儀を執り行われます。
日程は、火葬場の予約状況によって決定されます。
火葬場は、東京都内では、株式会社の運営もありますが、通常は公営で行われています。その為、その地域の火葬場の空き状況を確認する必要があります。日程を優先すると空いていない場合があり、その場合隣の県や隣の市の火葬場で荼毘にふします。
私の場合、平塚住民の方が亡くなった場合、平塚市の斎場であれば無料(もしくは格安)で利用できるのですが、火葬場が混雑していたことから隣町の火葬場を利用する事となり、火葬料として13万円?別途必要になりました。
当然、市民の為の火葬場ですので安く利用することが出来るのですが、時間を取った場合は、別の地域の火葬場を借りることとなり、その分費用も掛かる結果となりました。時間を優先するか?費用を優先するか?難しい所です。
日時と場所が決まったら、葬儀の形式なります

まず、一番に菩提寺のご住職に電話を入れることを忘れないように・・・
ここで、葬儀社と日時を買ってに決めてしまって、和尚さんに怒られたというケースも多々ございます。
亡くなったとこを知ると、急ぎ駆けつけて、枕経を唱えていただきます。
そして、通夜葬儀の打ち合わせと「戒名」について相談がります。
菩提のない方は、ご紹介されたお寺様に、故人の仕事や趣味 お人柄についてお話ししてください。
その方の事をじっくりとお話をお聞きしてご住職がお授け下さいます。
僧侶は、海外旅行にはいけない。

実は、知られていませんが、僧侶は海外旅行には極力いきません。
なぜなら、亡くなったと知れば、すぐに駆け付ける必要がある事から、海外ではすぐに帰国できない場合があります。
新婚旅行で海外にハネムーンしていたが、檀家さんが亡くなったことを知って、途中で帰国した話や、海外に降り立ったその足で別の飛行機で戻ってきた話。また、国内であれば、深夜車を走って北海道から東京まで帰ってきたなど、僧侶もとても大変です。
ですから、まずは、お寺様に連絡をして、日程の調整をなさってください。
葬儀に誰を案内するか?
ここでトラブルになるケースもあります。
人に声をかけると、どこまで案内すればいいのだろうか?
会社関係 趣味関係 近所関係 学校関係などなど
余談ですが、この時に事前に故人が案内先を用意していたら、どれだけ楽だったろうか?と思います。
それでなくとも、大変な時に、付き合い関係は本人しかわからない場合も多いからです。
エンディングノートは、とても大切であると実感する時です。
この時の注意点は、
1:声をかけた場合、一人が100名になる事も。
会社関係や学校関係の方一人に声かけたところ、その方が、伝言ゲームのように伝えてくださいます。
そうすると、喪主として予想していなかった方が会葬してくださることに。
嬉しいことですが、その後のお礼など、大変な事も多くあります。
2:声をかけておかないと後で関係が悪くなることや、弔問が大変
どうして、声をかけてくれなかった?と落胆されると共に、その後、ご自宅に弔問に来れれる方があります。
その都度に対応しなければならない事になり、困ったというケースもあります。
また、親戚の中で、連絡がなかったと関係が悪くなるケースもあります。
葬儀や法事などでないと、今では親戚が集まるという事は少なくなっています。
案内する事を忘れていたとなると、今後の法事・49日・初盆・1周忌・3回忌・7回忌と法事事も呼びにくくなります。
参列する?しない?は別として、親戚関係には声をかけておくと良いでしょう。
また、コロナや故人の遺志として、身内だけで・・・というケースでも、こういう理由で案内いたしませんが、生前のご厚情に感謝しますと一報入れておかれることをおすすめします。
5. ご納棺
納棺士が、納棺してくださいます。(映画おくりびとで注目を浴びました)
儀式・作法にのっとって、遺体を死出の旅路にするとともに、棺に納めます。

6. お通夜
いよいよ、お通夜です。
通夜とは、一晩中線香を絶やさず、遺体を守ると言われていました。ですから、寝ずの番がいて、線香をともすばかりに、火事になる事もあったそうです。本来は、葬儀の前夜祭というミニイベントではありますが、現代では、葬儀の時より、通夜の方が圧倒的に会葬者が多くあります。
皆さん、お仕事などあり、葬儀が来れない分、通夜は一晩中あるので、通夜にかけつけるといった流れです。
仕事が終わってから会葬するという流れに代わってきました。
余談ですが、我々、僧侶の衣体(法衣)も、通夜は略式の法衣で行っており、葬儀の時は、正式にきらびやかな法衣を用意しましたが、最近は通夜が盛大になってきたことから、通夜にも正式な法衣で行う場合も多くなりました。(そんな私の感想です)
この時に大切なのが「戒名」
戒名について

通夜の時に初めて披露されるのが「戒名」です。
枕経の時にお坊さんと打ち合わせをして、それまでに和尚さんが戒名を考えてきてくださいます。
戒名には、仏弟子とする大切な教えがあります
戒名は、付ける事ではなく、授かるものです。
通夜の法要後、和尚さんから、戒名について説明があり、生き様や姿勢を考える時であります。
戒名の種類には、信士・信女・居士・大姉・禅定門・禅定尼・院号居士・院号大姉・院殿号など、様々なランクがあります。
戒名のランクについては、詳しく戒名のページで説明いたしますが、原則は、すべて平等であるという事です。
戒名をお金で買うという考えの方もありますが、仏教やお寺への貢献度によって授かると別からの発想になります。
戒名は、商品ではなく、お布施ですので、いくらとして決まっているものではありません。(檀家さん達で決めているお寺もあります)
戒名という商品を買うのではなく、私たちのお寺を布施によって管理護持し、その布施でもって皆さんのためになる。
菩提寺のある方は、そんなに問題にされていませんが、菩提寺がない方にとって、初めて会った和尚さんに良い戒名を希望すればその対価としてのランクとなってきたことは、時代と共に変化してきたことに他なりません。
7. 告別式
通常、午前中に告別式が行われます。
正式には、葬儀式と告別式です
葬儀式とは、まさにこの時に宗教儀式を行い、故人を仏弟子として浄土にお導きいただきます。
告別式とは、お別れ会です。
よく聞いていると、葬儀式と告別式は別々のものであることがわかります。しかし、現在では一緒に行われていることからその事を知られる方も少なくなってきているように感じます。
僧侶が、戒律を授け、引導を渡す大切な法要となります(宗派によって戒律や引導がない場合も)
8. ご出棺
この時に霊柩車にのって葬列を組んで火葬場に向かいます。
昔は、宮殿型の霊柩車が主体でした。子供のころ、霊柩車を見たら親指を隠しませんでしたか?
親指を出していると、親が早死にすると変な迷信があったものです。
しかし、あの派手な霊旧自動車を見たときに、忌み嫌いされる方も多く、条例によって火葬場に乗り入れ禁止されるケースも出てきました。
ですから、今では、霊柩車とわからないような車が多くなりました。
親戚の方は、別のバスや自家用車にのって火葬場までついていきます
9. 火葬
火葬場につくと、葬儀社の担当が待っていてくれて、諸々の諸手続きをして下さいます
慣れないと何をしていいのかわかりませんので戸惑います。
火葬場や運転手への心づけ(地域によって禁止しているところも)など準備が必要です
火葬は、約1時間から1時間半 最近は早くなりました。
その間、静かに待っていることが普通でしたが、最近では、昼食の時間となり、弁当がふるまわれます。
控室で、食事をしながら火葬を待ちますので、思ったより早く終了します
10. 初七日法要と精進落とし
戻ってきて、初七日法要が行われます。
しかし、最近では、初七日は葬儀の中で組み込み(式中初七日)で行う場合が増えています
精進落としも、火葬場で食事をしているので、斎場に戻ってきて解散というケースも多くあります。
11.後飾りと諸手続き
自宅に戻ったら、後飾り棚を設置して、49日までは安置供養します。
この間、銀行・保険の書き換え、不動産や車などの動産の名義変更、保険の請求・役所の請求・などやることはたくさんあります。
49日は、あっという間にやってきます。施主だけでなく、家族の方が寄り添って手続き代行するなど負担を軽くしてあげてください。
悲しみのあまり、ショックで寝込んでしまわれる方もざらにあります。中には、悲しみと葬儀の準備の過労で、すぐに亡くなってしまい。ダブルの葬儀を行うことも有りました。精神的にも肉体的にも大変つかれる時間です
12. ご納骨・四十九日


49日法要の後に、お墓にある方は、納骨されます
白木位牌は、仮位牌と言って、49日までの死出の旅路に出たときの魂の休憩場所として考えます。(持論)
49日までに本位牌を発注されますが、専門の職人さんが作ってくださいますので、2週間ほどかかる場合があります
宗派によっては、位牌ではなく過去帳の場合も。
49日までに準備が必要ですので、間に合わないなどないよう、くれぐれもご注意ください
49日・納骨と終了してはじめて、ホッと出来る時です。
ご愁傷さまでございました。

ご質問の多いお布施の相場(目安)一覧
お布施の金額は、地域・宗派・お寺の方針・ご遺族のご事情によって幅があります。
下記は一般的に言われる目安です。実際には菩提寺や僧侶にご相談ください。
| 仏事・法要の種類 | お布施の相場(目安) | 備考 |
|---|---|---|
| 通夜・葬儀 | 20万~50万円前後 | 戒名料を含む場合あり。地域差が大きい。 |
| 初七日法要 | 3万~5万円 | 最近は、葬儀と同時に営む場合が多い。 |
| 四十九日法要 | 3万~10万円 | 葬儀の2割ほど。納骨法要と同時に行うケースが多い。 |
| 一周忌法要 | 3万~10万円 | 葬儀の2割ほど。会食(お斎)の有無で増減。 |
| 三回忌以降の年忌法要 | 3万~10万円 | 1周忌と同じ位。ご縁や関係性によって増減あり。 |
| お盆・お彼岸の参拝 | 1万円~5万円 | 地域差が大きい。自宅参拝はやや高め。 |
| 月命日・小規模法要 | 5千円~1万円 | 本堂参拝のみは低め。 |
| 戒名料(院号・居士/大姉・信士/信女 など) | 10万~100万円超 | 格式で大きく変動。近年は「一律3万円」の寺院も。 |
| 水子供養・個別供養 | 5千円~3万円 | 読経・位牌・納骨の有無で変動。 |
| 人形供養・仏壇供養 | 5千円~2万円 | 供養料と処分料を含むことあり。 |
お布施の考え方(クリックで開閉)
- 金額は本来「お気持ち」:無理のない範囲で、感謝とご縁に応じてお包みします。
- 内訳の確認:読経料・戒名料・車代・御膳料など、含まれる項目を事前に確認すると安心です。
- 表書きの例:「御布施」「御回向料」「御車代」「御膳料」など。